介護サービスの利用について
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要」と認定されることが必要です。
サービスを利用できる方
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護や支援が必要な状態と市に認定された方が、介護サービスの利用対象となります。介護や支援が必要となった原因は問われません。
第2号被保険者(40歳~64歳までの医療保険に加入されている方)
加齢が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要な状態と市に認定された方が、介護サービスの利用対象となります。(事故や特定疾病以外の病気が原因で介護や支援が必要となった場合には、対象となりません。)
特定疾病とは
介護保険で対象となる特定疾病は下記の16種類です。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、レヒ゛ー小体病等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービス利用の手順
介護サービスを利用するまでの手続きの流れは次のとおりです。
(緊急の場合は、申請日からサービスが利用できます。)
- 要介護・要支援認定の申請
- 訪問調査の実施及び主治医意見書の依頼
- 介護認定審査会による審査、判定
- 認定結果の通知
- ケアプランの作成
- サービスの利用開始
1.要介護・要支援認定の申請
申請場所
- 高齢者支援課介護保険係(光市総合福祉センター「あいぱーく光」内)
申請できる方
- 本人または家族
- 居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
- 成年後見人 …など
本人以外の方が申請する場合は、本人の承諾を得ており、本人の状態を理解している方が申請してください。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
(窓口に備え付けてあります。また、「介護保険に関する届出様式」のページからダウンロードできます。) - 介護保険の被保険者証
- 有効な医療保険被保険者証又は資格確認書
- 被保険者本人(介護のサービスを利用する本人)のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーを本人から預かる場合には委任状が必要です)
- 被保険者本人又は代理人の身元を確認できる書類
申請時には、次の事項をお尋ねします。
- 主治医の氏名及び病院名(主治医意見書の依頼に必要です。)
- 第2号被保険者の方の特定疾病(該当しない場合は申請できません。)
2.訪問調査の実施及び主治医意見書の依頼
訪問調査
市の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況等を調べるために、実際に確認動作をしていただいたり、本人と家族などから聞き取り調査を行います。(所要時間約1時間)
主治医意見書
本人の主治医に介護を必要とする原因疾病等についての意見書を作成してもらいます。意見書の依頼は市が行い、作成料は不要です。
3.介護認定審査会による審査、判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターで判定した後、医療・保健・福祉の専門家による介護認定審査会において、介護が必要な状態か、どの程度の介護が必要かを審査します。
4.認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、市が要介護状態区分を認定し、その結果を記載した認定結果通知書と被保険者証を送付します。
通知は、原則として申請から30日以内に届きます。
要介護状態区分に応じて、有効期間や利用できるサービス、介護保険で認められる月々の利用限度額が決まります。
要介護状態区分とは
| 要介護状態区分 | 心身の状態の例 |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的な日常生活はほぼ送れるが、家事などの身の回りの世話になんらかの介助が必要な状態 |
| 要支援2 | 歩行、立ち上がりなどが不安定で、家事や入浴などの身の回りの世話に一部介助が必要な状態 |
| 要介護1 | 歩行、立ち上がりなどが不安定で、家事や入浴などの身の回りの世話に一部介助が必要な状態で、状態の不安定さや認知症状が見られる状態 |
| 要介護2 | 歩行、立ち上がりなどが自力ではできないことが多い。排泄や入浴、衣服の着脱などに多くの介助が必要な状態 |
| 要介護3 | 歩行、立ち上がりなどが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要な状態 |
| 要介護4 | 日常生活の基本動作を行う能力がかなり低下し、起き上がりが自力でできないことが多い。排泄、入浴、衣服の着脱、食事摂取などの日常生活全般にほぼ全面的な介助が必要な状態 |
| 要介護5 | 日常生活の基本動作を行う能力が著しく低下し、起き上がり、寝返りが自力でできないことが多い。排泄、入浴、衣服の着脱、食事摂取などの日常生活全般に全面的な介助が必要で、さらに特別な配慮や介助が必要な状態 |
| 非該当 | 基本的な日常生活を行うことが可能であり、かつ、家事などの身の回りの世話にも介助を必要としない状態 |
非該当と認定された場合
介護サービスは受けられませんが、「基本チェックリスト」を受け、基準に該当した方は、介護予防・生活支援サービス事業を受けることができます。
また、市が行う介護予防事業(地域支援事業)や保健・福祉サービスなどが利用できます。
詳しくは高齢者支援課高齢福祉係にお問い合わせください。
5.ケアプランの作成
ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護サービスを利用するためには、ケアプランが必要です。
要介護1~5の場合
居宅介護支援事業所や小規模多機能型居宅介護事業所の中から事業所を一つ選び、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼するとともに、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市に提出します。
なお、施設入所を希望される場合は、希望する施設に直接連絡を取ります。
要支援1・2の場合
光市地域包括支援センターにケアプラン(介護予防サービス計画)の作成を依頼し、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を市に提出します。
6.サービスの利用開始
訪問介護や通所介護などのサービスを行う事業者と契約し、サービスを利用します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
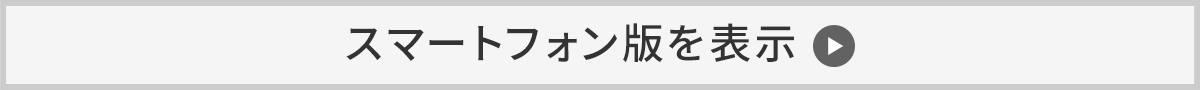













更新日:2020年03月02日