高額療養費
自己負担が高額なとき
高額療養費
同じ月内に支払った自己負担額(食事代や居住費、保険対象外の医療費は除く)が下表の自己負担限度額を超えたときは、超えた額が申請により支給されます。なお、該当する人には、診療月から約3か月後に申請書等を送付します。
70歳未満の人の高額療養費の計算方法
- 同じ病院・診療所でも歯科は別計算となります。また、外来と入院も別々に計算します。
なお、院外処方箋に基づく薬剤費は、処方箋を発行した医療機関の医療費と合算されます。 - 同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた額が支給されます。
|
所得区分 |
適用区分 |
自己負担限度額 |
|---|---|---|
|
上位所得者 901万円超 |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
上位所得者 600万円超901万円以下 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
一般 210万円超600万円以下 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
一般 210万円以下 |
エ |
57,600円 |
|
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
「多数該当」とは、同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合の、4回目以降の限度額です。
- 所得は旧ただし書所得の合計額:{総所得金額等-基礎控除(33万円)}の世帯合計額(国保加入者に限る。)
- 「住民税非課税世帯」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。
70歳以上75歳未満の人の高額療養費の計算方法
- 外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
- 同じ月の全ての医療機関で支払った自己負担額を合算して限度額を超えた額が支給されます。
|
所得区分 |
||
|---|---|---|
|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
| 現役並み所得者 現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者 現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者 現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
| 一般 |
18,000円 |
57,600円 |
| 住民税非課税世帯 低所得2 (低所得1以外) |
8,000円 |
24,600円 |
| 住民税非課税世帯 低所得1 (総所得金額が0円) |
8,000円 |
15,000円 |
「多数該当」とは、同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合の4回目以降の限度額です。
- 「現役並み所得者」とは、次のいずれかに該当する人です。
- 住民税課税所得金額が145万円以上の人
- 住民税課税所得金額が145万円以上の70歳以上の国保被保険者と同一世帯の人
ただし、次のいずれかに該当する人が申請した場合は、申請月の翌月から「一般」の適用となります。- 同一世帯の70歳以上の人の収入合計額が520万円(同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない人は383万円)未満の人
- 同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない収入383万円以上の人で、同一世帯の旧国保被保険者との収入合計が520万円未満の人
「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の被保険者の資格を有する人。ただし、世帯主が変わると旧国保被保険者ではなくなります。
- 「一般」には、70歳以上75歳未満の国保加入者全員の総所得合計210万円以下の場合も含みます(住民税非課税世帯を除く)。
- 「住民税非課税世帯」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。
- 「低所得者2」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
- 「低所得者1」とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、所得区分ごとに必要経費・控除を差し引いた各所得(年金所得は控除額を80.67万円として計算)がいずれも0円になる世帯に属する人です。
高額療養費の申請について
該当する人には、診療月から約3か月後に申請書等を送付します。
申請に必要なもの
- 高額療養費申請書(市役所から送付したもの)
- 資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 該当月の診療・調剤にかかる領収書
- 通帳(世帯主名義のもの)
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
高額な診療を受ける場合、限度額適用認定証を活用しましょう
受診時に「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、月々の医療費の支払いが所得に応じた高額療養費の「自己負担限度額まで」に抑えられます。また、住民税非課税世帯の人は、「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により医療費の支払いが自己負担限度額までになるとともに、入院時の食事代が減額されます。マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関で高額な診療を受けるときは、認定証の交付を申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証については下記リンク先の見出し「限度額適用認定証」をご覧ください。
75歳到達月の自己負担限度額の特例について(平成21年1月1日施行)
75歳到達月については、誕生日前(国保)と誕生日後(後期高齢者医療制度)における高額療養費の自己負担限度額が本来額の2分の1になります。
また後期高齢者医療制度への移行に伴い国保に加入することになった被用者保険等の被扶養者についても、移行前の健康保険と移行後の国保における自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。
高額の治療を長期間続ける場合
特定の疾病(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全等)による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により特定疾病の認定を受けることができます。
詳しくは、下記リンク先の見出し「特定疾病療養受療証」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
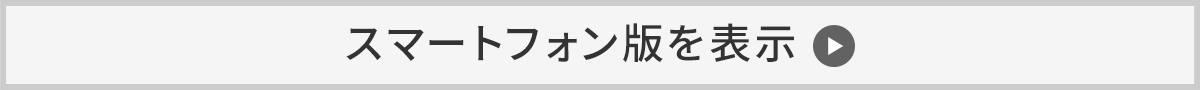













更新日:2020年03月02日