出張 ちょこっと利助くん!『国指定重要文化財 石城神社本殿~令和の大改修~』

現在、光市にある国指定重要文化財「石城神社本殿」の保存修理事業を行っています。
光市文化PR大臣「利助くん」が改修の様子を紹介します。
ホームページに掲載しきれない写真を光市インスタグラムでも、掲載していますので、ぜひ、みてください。
保存修理事業の概要は、下記のリンクをご覧ください。

光市文化PR大臣 利助くん
利助くんは、光市の様々な文化を紹介するキャラクターです。
日頃は、「ちょこっと利助くん!」で伊藤公資料館を紹介していますが、今回は出張で石城神社へやってきました。
「利助」は光市生まれの初代内閣総理大臣伊藤博文の幼名です。
改修の様子
改修前
屋根

今回の改修の主要な部分となる屋根。

長年の雨等で欠けや腐りが目立ち、動物が開けたと思われる穴もありました。
(フクロウかキツツキではないかとのこと。)

こけら葺き拡大写真
こけら葺き
石城神社本殿の屋根は「こけら葺き」という手法で作られています。
「こけら」とは、杉などの木材で作った3mmの薄い手割り板のことであり、「こけら葺き」とは、このこけらを丁寧に貼り重ね竹釘で打ち、屋根を作る手法です。
この技術は、1300年以上の歴史を持ち、国の選定保存技術に選定されており、文化財に多く使われている古くから引き継がれてきた職人の匠の技です。

こけら葺きに使用する竹釘の写真
今回の改修では、このこけらを全てはがし、新しいこけらに葺き替えます。
木部

石城神社本殿の壁や縁回りを木部といいます。

手すりや床など、自然に晒されているため、腐食している箇所が多くあります。

今回の改修では、木部の腐食している部分の補修を行います。
宮殿

宮殿は、石城神社本殿内部に安置されています。「宮殿」と書いて、「くうでん」と読みます。宮殿と棟札(2枚)は、本殿とあわせて文化財に指定されています。

宮殿の角など、折損や欠損している箇所があります。

今回の改修では、宮殿の折損、欠損している細かな部分の補修を行います。
改修中

令和4年1月に安全祈願祭を行い、工事が始まりました。

玉垣撤去の様子(左:撤去前、右:撤去後)
はじめに、玉垣を撤去し、足場を設置しました。

石城神社全体がドームに覆われた状態になっています。
こけら葺きの改修

こけら葺き作業中の様子
一般的なこけらは3cm間隔ですが、石城神社のこけらは2.4cm間隔であるため、一般的なこけら葺きの建築物の1.25倍のこけらが必要になります。

こけら葺き(左:改修前)
石城神社は周囲を山に覆われているため、湿気が多く、傷みやすいのですが、こけらの間隔を狭くし、たくさんのこけらを使用することで、耐久性を高めています。

また、屋根の端のカーブ周辺のこけらをよく見ると、途中からこけらの横列が増えています。
屋根の形状に合わせて、違和感のないようこけらの列を加減しています。
木部の改修

今回の改修では、木部の腐食した箇所の補修も行います。
縁束(石城神社のまわりを支える短い柱)の半分から下の部分も接ぎ木による改修しています。
古い木と新しい木の違和感をなくすため、古い木の長年の汚れにあわせた木材を使用しています。

また、よく見ると、新しい木の方が数ミリ大きく作られています。
これは、今後、新しい木は乾燥し縮んでいくことが予想されるため、その縮み幅を見越しているそうです。
100年後には、上の古い木と同じ大きなになることを計算して改修しているようです。
工具

木を削る「槍がんな」
文化財を改修するための工具を紹介します。
木を削る作業において、現在は台がんなを使用することが一般的で、槍がんなを用いる手法は室町時代の特徴の一つです。

本殿の扉に拓本をしたことで、槍がんな使用の跡がみえる
改修の際、本殿や宮殿の扉に槍がんなを使用して削った跡が見つかりました。
凹凸のある物に紙を置き、墨色をのせることで形状を写し取る「拓本」という手法により、扉に槍がんなで削ったときにできるさざ波のような跡があることがわかります。

木を削る「台がんな」

木を平らにする「手斧(ちょうな)」

木を切る「木挽き(こびき)」
見学会
現場見学会(令和4年8月20日、21日)

こけら葺き見学の様子
8月20日(土曜日)、21日(日曜日)に現場見学会を実施しました。
2日間で合計116名の方に見学いただきました。

こけら葺き見学の様子
見学会では、実際に改修工事に携わる人たちから、
- 石城神社や改修工事の説明
- こけら葺き等の作業見学
- やりかんなの実演
- 改修工事にかかる部材や工具の紹介
が行われました。

やりかんな実演の様子

部材や工具の紹介の様子
完了見学会(令和4年11月19日、20日)

こけら葺き解説の様子
10月末に保存修理事業が終了し、11月19日(土曜日)、20日(日曜日)に完了見学会を実施しました。
2日間で合計74名の方に見学いただきました。

保存修理技術解説の様子
工事担当者から今回の石城神社本殿保存修理の内容や文化財保存修理技術について、解説が行われました。
また、石城神社周辺に所在する歴史文化遺産、神籠石や第二奇兵隊について解説が行われました。
今回の改修で発生した廃棄木材を活用して作成したカードスタンドを参加者全員にプレゼントしました。

石城神社周辺の歴史文化遺産解説の様子

廃棄木材を活用したカードスタンド
改修後
令和3年11月から実施していた石城神社本殿の改修工事が令和4年10月に完了しました。

改修後の石城神社本殿

屋根

屋根(左:改修前、右:改修後)
今回の屋根葺替え作業では、約4万枚のこけら板を使用しました。改修前のこけら葺き(昭和59年葺替え)はサワラのこけら板を使用していましたが、今回は当初使われていたと思われるスギを使用しています。
また、そのこけら板は職人が一枚一枚手割りして製作しています。大量に必要となるため、機械で量産した方が時間もコストもかからないのですが、手作業で割ったこけら板は、縦に重ねた時に隙間ができ、蒸れて腐ることを防ぎます。

こけら葺き
こけら葺きを行う際は、こけら板を事前に水につけて膨張させた状態で葺いています。乾燥している状態でぴっちり詰めて葺いた場合、湿気の多い6月にはこけら板が水気を含み、反りあがってきてしまいます。膨張した状態でこけら板を葺くことで、反りあがりを防止しています。よって、乾燥した状態では、少し隙間があいた状態になっています。
木部

木部(左:改修前、右:改修後)
縁廻りなど木部の腐食している箇所を補修しました。

木部(上:改修前、下:改修後)
縁板(床板)を横から見ると、年輪(木目)が上向きのもの、下向きのものがあり、バラバラです。これは、改修前の年輪の向きに合わせています。

今現在、この年輪の向きの意味は分かっておらず、建設時、年輪の向きは関係なく綺麗な面を上に使っただけかもしれません。しかし、何か意味がある可能性もあります。そんな様々な可能性を考えて、年輪の向きまで正確に引き継いでいます。
宮殿

宮殿細部(上:改修前、下:改修後)
本殿に安置されている宮殿の欠損している細部の補修を行いました。

扉に槍がんなの使用跡や細部の意匠等室町時代の特徴が見受けられました。
番外編
蟇股(かえるまた)

側面の蟇股
カエルが座っているような形状の部材で、様々な模様があり、本殿の正面・向拝・側面それぞれに違った蟇股があります。
蟇股は、石城神社本殿が再建された室町時代の特色の一つであり、石城神社本殿の蟇股は秀作といわれています。

向拝の蟇股

正面の蟇股
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化・社会教育課 文化振興係
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3607
メールアドレス:bunsya@edu.city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
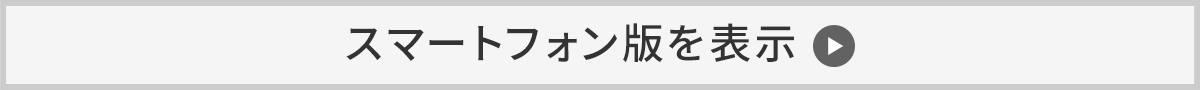













更新日:2023年02月10日